
正装クバヤについての記事で、「カルヨ(大祭)では女性も頭に白いハチマキを巻きます」と書きました。
でね、奥さん。
この白いハチマキの名称、3回ぐらい聞いたのに記憶からすっかりファラウェイしまして。ネット検索したものの、コレ!というのが出てこないんですよ。
数人にリサーチしたところ…なんと地域によって呼称がまったく異なることが判明しました。そりゃ検索してもヒットしないですわ。
ちなみに男性が頭に巻く布は、バリ語で「Udeng(ウダン)」といいます。島内全域、この呼称です。
ローマ字読みだとウデンですが、このeは“エ”の口の形で”ア”の発音なのでウダン。最後のngはングだけど、グはほぼ発音なし(気持ち鼻にかけたン)。
実は今年3月からバリ語の歌を習い始めたんですけどね、これらの発音が難しいのなんのって。
すべてのeがa、aがoの法則ならわかりやすいのに単語によって異なります。なんで?
白紐の名称
リサーチで得た5つの呼称を紹介します。地域によってほかの別称もあると思います。
◆ 全域:Pita Putih
まず、オダラン(寺院建立祭)やカルヨで奉納演奏しまくってる友達に聞いてみました。
「あれの正式名称、私も知らないです…。Pita Putih(ピタ プティー)と呼んでます」と。
舞踊の先生いわく「ピタ プティーはバリ全域で通じる総称。素材名に近い。Pita=リボン、紐。Putih=白。
男性のウダンをKain Katun(カイン カトゥン)=綿布、と呼ぶのと同じ」と。
え?ウダンの素材名はカイン カトゥンなの?! 調べてみるとIkat Kepala(イカッ クパラ)=頭紐とも。
特定の地域ではなく、あちこちで言うなら、ピタ プティーがベターかもしれません。
◆ ウブド:Bebed

続いて、ウブド在住の友達がバリ人に聞いて、LINEで教えてくれました。
「プリアタンではBebedと呼ぶそうです。発音が難しくて日本語だと書けません」と。
Bebed(ブベッ)ですね。
インドネシア語もバリ語も1文字目の母音eは“エ”の口の形で”ウ”の発音なので、ブ。それ以降のeはローマ字読みで、ベ。最後のdはッ(促音)。
ウブドのプリアタン以外もこの名称かは不明です。
◆ バトゥアン:Saet

ウブドと同じギャニャール県ですが、バトゥアンでは「Saet(シーッ)」と呼びます。まんまローマ字読み。なぜか英語っぽく。最後のtはッですが、流し読みでも問題なし。
まさかバンジャール(町内会)で呼び方変わらないよね~?と、隣の町内会同士の舞踊の先生とガムランの先生に聞いてみましたが、どちらも同じでした。
近隣デサ(村)、たとえばスカワティやシンガパドゥでは異なるかも?
◆ クロボカン:Memuker
クロボカンクロッドに住むバリ人友達宅へわざわざバイクで聞きに行きました。えぇ、これだけのために。
「ガベンのあとのお祭りで頭に付ける白紐ね、Memuker(ムムクル)。どこもそう呼ぶでしょ?」と。
いやいやいやいや。全然違います。共通点1つもなし!
1文字目の母音eは“エ”の口の形で”ウ”の発音、次の母音uはまんまウ、なのにその次は母音eは1文字目と同じ。最後のrは巻き舌ぎみにル。
ムムクルまたはMamukur(マムクル)は白紐に限らず、火葬儀式で使われる用語の1つのようです。
bukurが語源で、「天への扉」という意味。死者の魂が神々の領域へ入ることができるように、「浄化して昇華させる儀式」を指すようです。
◆ バトゥリティ:Pekir
近所のチャナン(お供え)屋へ行ったら、「昨日までオダランで帰省してた」というので、さっそく聞いてみました。
タバナン県の棚田ジャティルウィに近いバトゥリティでは「Pekir(プキル)」と呼ぶそうです。
1文字目の母音eは“エ”の口の形で”ウ”の発音、最後のrは巻き舌ぎみにル。
一般的に、プキルまたはPlekir(プルキル)は上記写真にあるような「後頭部に扇状のヒラヒラがついた紐」を指す場合が多いです。
また女性の髪飾りやバリ舞踊のグルンガン(冠)に挿す金の花もそう呼ぶとなんとか(あいまい)。
女性の髪形
今回白紐についてネット検索して、関連記事でもっとも驚いたのは神事の女性の髪形についてです。
正装クバヤについての記事では、「オダランでは髪の毛は肩についたら結ぶのが基本。だらりと下ろしたままでは神様に失礼」、「結婚式では恋人募集中なら髪の毛は結ばずおろしておく」と書きましたが、ちょっと違ってました。
◆ 正装時のヘア名称
3種類あります。
- Pusung Gonjer(プスン ゴンジェール):
未婚女性のみ(基本は10代)。前髪を下ろして、後髪をまとめたスタイル。
これは「女性が男性を選ぶ自由と選ばれる自由を持っている」という目印(恋人募集中)。 - Pusung Tagel(プスン タゲル):
既婚女性。髪の毛をすべて束ねて(前髪は作っても下ろさない)、長ければ後ろは団子状に。
寺院内でのお祈りや伝統行事に参加するときの一般的なスタイル。 - Pusung Podgala(プスン ポドガラ)=Sulinggih(スリンギ):
聖なる女性(Suci)向け。前髪含めてモリモリのアゲアゲにし、扇というか蝶のような形に。
文字での説明が難しいのですが…メガワティ元大統領や、個人的に大好きなマンデラケイコさんの髪形を想像していただければ。
正式にはトリ ムルティの象徴であるブラフマー神=黄色いチェンパカの花、ヴィシュヌ神=白いチェンパカの花、シヴァ神=サンダットの花を飾る。
◆ 髪をまとめる理由
個人宅で行われるウパチャラ ニカー(結婚式)やその他ウパチャラ ポトンギギ(成人儀式)以外で、髪の毛を下ろしている女性ってあまり見かけないんですよ。
特にカルヨアグン(大祭)やドゥドナンカルヨ(死者を弔う大祭)など寺院の大祭では、たくさんの写真を見返しても10代の若い女性含めてほぼ全員ひっつめ髪。
いろいろな記事を読むと「清潔さを保つため」と書いてありますが、単なる清潔さなら長髪より短髪のほうが洗いやすいし、乾かしやすいはず…(あてくしは長髪な)。
と思ったらね、奥さん。
個人の清潔さではなく、寺院内を清潔に保つためなんですって!!
舞踊の先生いわく「昔は今ほどシャンプーが良くなかったし、水も出なかった。川で沐浴したりも。なので寺院内に毛やフケを落として汚さないようにまとめる必要がある」と。
「神様に失礼」というより「神聖なエリアに個々が敬意払って入る」という感じですかね。
それが今も続いているため、大祭ではキッチリしたまとめ髪が基本。
外国人は大目に見てもらえますが、前髪はまだしも後ろ髪まで下ろしていると「あれはちょっと…」「誰にも教えてもらえなかったの?」と指をさされる可能性大。特に年齢が高いバリ人ほど快く思わない傾向にあります。その方を思うなら、誰かそっと教えてあげましょう。
男性の頭紐
抜け毛なら女性より男性のほうが…と思っちゃったあなた。
そう!だから男性はつねにウダンを巻く(かぶる)のです。家寺だろうが大祭だろうが必須ですもんね。
ウダンが上向きなのは神への崇拝として。
結び目は思考を集中する=ngiket manah(ンギケット・マナ)の象徴で、額の真ん中に配置されます。
左右非対称で、右側が盛り上がっています。これは善悪で、右=善寄りに行動しようという意味が込められています。
また、結び目の端は、右=ヴィシュヌ神、左=ブラフマー神、下=シヴァ神を表します。
◆ ウダンの色
PHDI(インドネシア・ヒンドゥー教協会)より色と意味が指定がされています。
- 白色:
寺院用。自然への回帰、心の明晰さと平和、自己の純粋さの象徴として。 - 黒色:
火葬用(葬式の火葬より前)。喪に服す。悲しみを表す。 - それ以外の色:
寺院と火葬以外の社交活動の場。
◆ ウダンの巻き方
3種類あります。
- Udeng Jejateran(ウダン ジゥジャテラン):
一般的なバリ人男性が寺院や社会活動で着用。 - Udeng Kepak Dara(ウダン クパッ ダラ):
伝統的指導者が着用。王様や村長などリーダーとして人々を守る能力の象徴として頭に覆いがある。 - Udeng Beblatukan(ウダン ブブラトゥカン):
宗教指導者が着用。後ろで下向きに結ぶ。個人よりも公共の利益を最優先するという意味も込められている。
男女はニコイチ
マンクーに聞いてみた(その2)で書いたとおり、バリヒンドゥー教では「夫婦は運命共同体」とみなされます。
正装についても実は男女がニコイチのセットになってるんですってよ。
- Kaman(カマン):
下衣となる腰布です。
男性は右前になるよう右から左に巻きます(反時計回り)。真理またはダルマを守らなければいけないという象徴。折り目になる布の先端は地面につかないギリギリにし、女性よりも大きな責任を負って、前進するという意味が込められています。
女性は左前になるように左から右に巻きます(時計回り)。男性とのバランスを保ち、彼らが責任を遂行するのを見守る役目があります。 - Saput(サプッ):
男性がカマンの上に、同じく反時計回りに巻きます。外部の悪影響から守ってくれると考えられています。 - Selendang(スレンダン):
女性がクバヤのウエストに巻く帯紐です。悪意を抑制するだけでなく、子宮を守り、上下半身を区切るものとして扱われます。
調べてみると、それぞれに理由と意味があるんですね。勉強になります。
白紐から思わぬ方向に広がりました。深いわ~。
では、ごきげんよう。

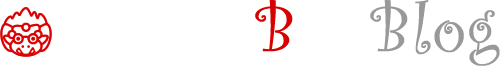






 バリ島ランキング
バリ島ランキング